忙しい人のための特撮怪獣映画概論その①【誰得】
2013年7月14日 特撮
自分は特撮怪獣映画が大好きである。あらゆるサブカル含めてみてもやっぱり一番好きなのはコレだし、幼少期から小学校高学年あたりまでは教育番組や他の子供向け番組の代わりに特撮映画を見て育ったといっても過言ではない。
そのくらい自分の中に根付いている特撮映画であるが、最近またシリーズを見返すことがあり、子供のころは只々怪獣がカッコいいとか爆発スゲーとしか感じなかったのが、自分自身が大人になったからか「この 作品はこの技術とか描写がすごいなー」とか「このレベルの演出・ストーリーだったら大人の鑑賞に耐えるレベルの映画として他人にもお勧めできるなー」とか考えたりもできた。
で、これはいい機会ということで、「これだけ観とけば特撮怪獣映画のなんたるかが分かる!」といった感じのリストを作ってみようと思い立った次第である。特撮怪獣映画というあまり一般受けしないディープなジャンルの入門として見なくても、今回選んだのは単なる怪獣映画としてではなく大人の見る邦画としても十分通用するクオリティのものを選別したつもりなので、単純に「面白い映画が観たい」と いう需要にも応えられるものではないかな、と思う。
チープな文章になるかもしれないが、この記事を見て特撮怪獣映画に興味を持ったなら、ぜひ近所のビデオ屋でDVDをレンタルすることをお薦めする。
----------------------------------------------------------------------
さて、「特撮怪獣映画」と一概にいっても種類・本数が多く、ウルトラマンなどのヒーロー物も含めればとても完璧にカバーできるものではない。従って、今回まとめる範囲は「製作会社として主に東宝・大映から映画として配給された”怪獣が主役の”作品」に限ることにする。ウルトラマンシリーズなどテレビ・OVAを主体としたヒーロー物は含まれていない。こちらもこちらで面白いものは沢山あるんだけども。。。
また、映画の質を評価する基準として、私的なものではあるが【リアリティ】【特撮技術】【ロマン】の3つを考慮することにした(あくまで主観的なものなので、あしからず)。一つ目については、「巨大な怪獣が人間世界に現れる」という非日常な現象を、役者の演技だったり背景設定やストーリープロットであったりにより、どこまでフィクションを感じさせない現実感を伴ったものとして表現できているか、評価した。二つ目では、ミニチュアセットの組み方や怪獣の操演、破壊・爆発描写など、特撮映画が特撮映画たる技術を、どれだけ高いレベルで活用出来ているか、ということを重点的に評価した。最後の【ロマン】であるが、【ロマン】って何ぞやということを言い出すと人それぞれで概念が分かれるので、あくまで自分にとってのロマン性を基準にすることにした。項目の詳細については後ほど説明することとする。
このリストでは、上記の三つの評価項目に照らし合わせ、特にポイントの高いと思われる各作品について、見どころなどを紹介したいと思う。基本的に自分はシリアス志向の怪獣映画が好きで、人に勧めるならそういったものの方がいいとも考えているので、コミカル色の強い作品についてはそれが例え優れた作品であってもここには挙げないようにした(例えばキングコング対ゴジラなんかはこの例になる)。
---------------------------------------------------------------------
【リアリティ】
①「ゴジラ(1954)」
あのゴジラが、最後の一匹とは思えない。
≪基本データ≫
1954(昭和29)年11月3日上映 (併映:仇討珍剣法)
配給:東宝
観客動員数:961万人
製作:田中友幸
音楽:伊福部昭
特殊技術:圓谷英二(円谷英二)
監督:本多猪四郎
≪ストーリー≫
事件は一艘の貨物船の沈没事故から始まった…。救助に向かった船もまた炎上・沈没。大戸島に流れ着いた生存者は恐る恐る『巨大な怪物に襲われた】と語る。そして嵐の夜、その巨大な怪物は大戸島に現れ暴れまわった。
山根博士らは政府の命を受け災害調査団を結成し、大戸島へと向かう。博士の前にも姿を現した巨大怪物は、大戸島の伝説からゴジラと名づけられる。ゴジラは度重なる水爆実験により住処を追われて現れた怪物であった。一方、山根博士の娘・恵美子はかつての婚約者・芹沢を訪れる。そして彼の家で『オキシジェン・デストロイヤー』の実験を目の当たりにし、驚愕するのだった。決して口外してはならないと恵美子に告げる芹沢であった。
そしてゴジラは東京に上陸。放射能火炎により首都東京を火の海と化す。防衛隊の抵抗も効果のないままにゴジラは東京湾へと去っていった。ゴジラによる被災者に触れ悲劇の再来を避けたいと願った恵美子は尾形に『オキシジェン・デストロイヤー』のことを明かしてしまう。水中の酸素を一瞬のうちに無くし全ての生命を液化させる魔の存在…。しかし、あの巨大な怪物を葬るには、この悪魔の薬に手を染めるしかない。兵器化されるのを怖れる芹沢は頑なに『オキシジェン・デストロイヤー』の使用を拒否するのであったが、いつ訪れるとも知れないゴジラによる災害、被災者の姿を見た芹沢は一度だけの使用と決め、『オキシジェン・デストロイヤー』によって東京湾に潜むゴジラに一人で立ち向かっていく…。
≪総論・見どころ≫
「特撮怪獣映画」っていってこの「ゴジラ」を挙げないのは、マウントポジションでぶん殴られても文句は言えない所業。特撮怪獣映画という狭いジャンルだけでなく、日本映画全般においても抜群の知名度を誇るゴジラシリーズ、その第一作にして最高作である。ハリウッドでも公開され大ヒットとなった。本作があったからこそ、今日の特撮怪獣映画があるのだといっても過言ではないだろう。「特撮」という技術についても、今作によって、主に戦時中の戦意高揚映画の中で使われ戦後見捨てられかけていた特撮技術の価値が再認され、解体されかけていた「特殊技術課」が東宝内に再編成されたという経緯がある。そんな有名映画「ゴジラ」であるが、はそもそもが「子供向けの怪獣映画を作りたい」というモチベーションから製作が始まったわけではない。当時の時事として、ビキニ環礁での水爆実験と、第五福竜丸の被爆事件が社会問題となっていたことを受け、これに着想を得た田中氏によって「ビキニ環礁海底に眠る恐竜が、水爆実験の影響で目を覚まし、日本を襲う」という 企画が立てられた。そんな生い立ちを持つ本作が持つメッセージとは何かを考えてみると、勿論怪獣という架空の巨大生物の魅力というのもあるだろうが、それ以上に「核兵器への恐怖、決して癒えない戦争の傷跡」といったものに注視すべきであろう。作中ゴジラが東京を襲う際の侵攻ルートがB-29爆撃機の東京空襲ルートと全く同じという描写もあるし、ゴジラから逃げ遅れた母子の発した、迫りくる恐怖を前にしながら「もうすぐ(恐らく戦争で死んだ)父ちゃんのところに行けるからね」というセリフも印象的である。このように、ようやく戦争の傷跡から立ち直りかけた日本を、日本人の記憶に戦争の忌み子として最も色濃く刻みつけられている核兵器より生まれ出でた巨大怪獣が襲い首都東京を火の海にする、というストーリーは、強烈なインパクトとリアリティを伴い当時の観客に叩き付けられたのではないかと察せられる。それほどまでに、本作の内包する、単なる娯楽映画としてではなく骨太な社会派映画としての演出は現実味溢れるものなのである。ゴジラ登場時、人々が恐慌し逃げ回るシーンや、襲撃後死傷者で溢れかえる病院の悲惨なシーンなどでもエキストラがしっかりと演技しており、「未知なる=予知・迎撃手段のない巨大生物がいきなり都市部に現れたらどうなるか」という、後の特撮怪獣映画ではタブー とされがちだった命題が明確に的確に描かれている。
なお、当リストでは本作を【リアリティ】部門の中で紹介しているが、潤沢な予算と若き円谷組の意欲と試行錯誤によって実現されたハイクオリティなミニチュアセットや、音響・操演などの工夫など、特撮技術それ自体に関しても勿論後続の映画とは一線を画すレベルがあるので、こちらもぜひ注目してほしい。
以下見どころ
・大戸島にて~ゴジラ出現~
よくこの映画(というかゴジラ映画)の名場面として挙げられるシーン。元々はホラー映画を意識して作られたという本作では、作中初めから未知なる巨大生物の存在が示唆されるものの、肝心のゴジラは中々姿を現さない。劇中中盤に差し掛かろうかというタイミングで浮かび上がってくる伝説の怪獣「呉爾羅」。作中 の人物や映画を見ている観客が「ゴジラ」という怪獣を意識し、実像を各々にイメージしかけたころ、なんの前触れもなく大きな足音と共にいきなりそれが現れることになり、初めて怪獣映画を見る人はこれまでのギャップも相俟って大いに驚くことだろう。
・オキシジェン・デストロイアーの資料を燃やす芹沢博士
基本的に自分は怪獣映画において「人間を主体にしたドラマ」は必要ないと思っている。怪獣映画の主役は怪獣であり、映画に登場する人物はそれに巻き込まれる有象無象に過ぎず、群像劇ならばまだしも個人として怪獣を差し置いてスポットを当てられる存在であってはならないからだ(なのでそこらへんが過剰に演出されているミレニアムシリーズとかはあまり好みではない)。しかしながら、只々怪獣が暴れまわったりプロレスしているだけの映画もまた妙味に欠けるわけで、 その中に如何にさりげなく、しかして印象的に人間の心理(苦悩・葛藤)や奔走などを差し込むか、というのはリアリティを求める怪獣映画には必須な要素である。そして「ゴジラ」はその意味で最も成功している作品であるといっても過言ではなく、それが最も色濃く表れているのが芹沢博士関連の描写。戦争によって顔の半分を奪われ、さらにその戦争の禍根ともいえるゴジラによって自らの半生を費やした研究の成果を犠牲にせざるを得なかった彼の心情描写は、この物語には必要不可欠なスパイスであろう。彼の結末を考えれば、オキシジェン・デストロイアーの使用を覚悟し、後の世のために関連資料を全て荼毘に伏そうとと手に取り、数秒の間自身の人生の結晶であるそれらを見つめる博士が何を思ったのか、怪獣映画ファンではなく、いち研究者を目指すものとしても強く感情移入した場面である。
②「フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ(1966)」
「第1プラス線よし!第2マイナス線よし!」 「第4マイナス線よーし!」
≪基本データ≫
1966(昭和36)年7月31日上映
配給:東宝
製作:田中友幸、角田健一郎
音楽:伊福部昭
撮影:有川貞昌、富岡素敬
監督助手:中野昭慶
特技監督:円谷英二
監督:本多猪四郎
≪ストーリー≫
嵐の夜、三浦半島沖を航行する漁船・第三海神丸が大ダコに襲撃され沈没した。ただ一人、生き残った男が「仲間は全員、タコに続いて海から現れたフランケン シュタインみたいな怪物に喰われた」と繰り返し、さらに、噛み砕かれ吐き出されたかのような乗組員の衣服が引き上げられたことを受け、海上保安庁はフラン ケンシュタインの研究で有名な京都のスチュワート研究所へ連絡を取った。
スチュワート博士は「研究所で育てられ、1年前に富士で死んだはずのフラ ンケンシュタインが生き返り、漁船を襲ったのではないか」との問いに「仮に生き返ったとしても海にいたり人間を喰うことはあり得ない」とし、サンダと名付 けられたこのフランケンシュタインの世話をしていた所員の戸川アケミも「サンダはおとなしく素直だった」として、これらの疑いを全面否定する。
し かし、その後も三浦半島付近では海の怪物による被害が相次ぎ、スチュワート博士とアケミはフランケンシュタインの目撃報告をもとに富士山へ、間宮博士は横須賀へ、それぞれ向かった。果たして引き上げられた漁船からは海棲生物の細胞組織が、また山中では巨大な足跡が発見された。間宮の持ち帰った細胞組織がフ ランケンシュタインのものと判明した直後、曇天の羽田空港に巨大なフランケンシュタインが現れ、女性事務員を食らう。雲間から太陽が覗くや、そのフランケンシュタインは大慌てで海へと姿を消した。
一連の事件がフランケンシュタインによるものと判明し、対策会議に出席するため上京するスチュワート博士とアケミ。博士は山と海とにそれぞれフランケンシュタインがいるのではないかと想像する。会議では強い光や火に弱い海のフランケンシュタインの性質が間宮によって指摘され、市民に灯火要請が出される。その夜、遊覧船を襲ったフランケンシュタインは、ライトを浴びせられ境川から上陸。自衛隊によって太田橋付近の谷川へと誘導され、殺人光線による細胞組織の徹底消滅を図る「L作戦」が実行される。メーサーと放電攻撃によって感電死寸前となる怪物。ところがそこに、さらに巨大なもう一匹のフランケンシュタインが現れ、自衛隊を牽制して海の怪物を連れ去った。
≪総論・見どころ≫
設定などは異なるが、前年に公開された怪獣映画『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(こちらも後で紹介)の姉妹編、日米合作の特撮映画で、ホラー映画(あるいはSF映画)や小説として超有名な「フランケンシュタイン」を特撮映画に持ち込んだ意欲作。今年公開されたハリウッド版特撮映画「パシフィック・リム」の監督ギレルモ・デル・トロ氏もお気に入りの一品である本作が他の怪獣映画に比べ最も異質に映る点は、 「人間の姿をした巨大怪獣同士が争う」という点で、ごみごみした着ぐるみを着た怪獣同士のずんぐりむっくりした闘いには見られない柔軟性とスピードに富んだアクションには一見の価値がある。
本作において特にリアリティを感じる要素を挙げるとするならば、「自衛隊の本気」「怪獣による人間の捕食」の2点である。まず前者であるが、今作はフランケンシュタインVSフランケンシュタインVS自衛隊といいくらい、怪獣同士の争いの中で人間が被害者としてではなく同じリングに立つものとしてフィーチャーされている。上述の「ゴジラ」で言及 した等身大の人間ドラマは比較的少ないが、一方で本作において人間はただただ蹂躙される立場には収まらず、ひたすらプロレスを続ける怪獣同士の間に、自衛隊という人間の組織が割って入るという構図が取られる。この、自衛隊の面々が怪獣に対し徹底抗戦を取る姿が、本作においては非常に迫力たっぷりに描かれているのである。特にガイラに対するL作戦の準備シーンは見ごたえ抜群。太田橋付近の谷川において、野をかけ山をかけ、川にも飛び込みながら放電装置を設置する自衛隊員の様子はさながら実際に災害出動における作戦行動を行っているように見えた。(この自衛隊員は全て俳優を使っているそうで、実際幹部職には俳優名が当てられているのだが、ヒラの自衛隊員もそうなのかな?だとしたら本当に真に迫るすごい演技)
そしてもう一つが「人間を食べる怪獣」の描写。怪獣というのは第一には恐怖感を煽る存在でなければならないと自分は思っている。その恐怖感を煽るための要素というのが、都市部や町村の建築物の破壊だったり、人間を踏みつぶしたり焼き殺したりする様子だったりするのだが、最も強烈なのが「人を喰う」という設定であろう。実際自分より遥かに大きくて明らかに強暴そうな生物を見たら、人間はまず初めに「喰われるかもしれない」と恐怖するに違いない。本来被食者には成り得ない人間が「喰われる」という原始的恐怖を覚える存在。これもまた怪獣の魅力の一つである。怪獣映画が子供向きなものにシフトしていくにつれてこのような残虐表現はなくなっていったが、昭和初期には、本作をはじめとして「食人シーン」を含んだ怪獣映画は珍しくなかった。それらのうち、最も直截的に「人を喰う怪獣」を描いたのがこの作品におけるガイラである。何より恐ろしいことに、前述したとおりこの怪獣は人型なので、 演出の利点としていきなり走ったりなど、人間と同じような敏捷な動きが再現できるわけである。人を喰う怪獣が、ゆったりとしたスピードではなく猛ダッシュで迫ってくる・・・というのは言い様のなく恐ろしいこと。その点を効果的に演出し、怪獣の本来持つ根源的な恐怖を印象強く表現できていることが、本作品の最も特徴的な点でもあるだろう。
以下見どころ
・ガイラの羽田空港襲撃シーン
トラウマ。何が怖いって、女性を噛み千切るようにムシャムシャする食人シーンもそうだが、日光を感じ取ったガイラが一目散に海めがけて疾走して去っていくところ。自分を喰おうとしている怪獣が、こんなスピードで向かってきたら絶対逃げられないなと思う。
・自衛隊によるL作戦実行シーン
後々の特撮映画において人間側の主力兵器として活躍する「メーサー殺獣光線車」の初お披露目もこのシーン。「この威力!」。メーサーからのマイクロ波の当たった樹木がなぎ倒されていくさまも、特撮技術として妙味のある演出だ。
③「ゴジラ(1984)」and「ゴジラVSビオランテ(1989)」
ゴジラ(1984)
君たちは原子力発電所を襲うゴジラを見て何も感じなかったか?30年前その姿を現すまで、ゴジラは伝説の怪物だった。こうした伝説は世界中の神話に見られる。ゴジラは人類に対する滅びの警鐘だ。
ゴジラVSビオランテ
兄弟などではない。文字通りの分身だ。同じ細胞で一方は『動物』・・・ 一方は『植物』。
≪基本データ≫
ゴジラ1984
1984(昭和59)年12月15日 公開
配給:東宝
観客動員数:320万人
製作・原案:田中友幸
特別スタッフ:
竹内均(東京大学名誉教授)
青木日出雄(軍事評論家)
大崎順彦(工学博士)
クライン・ユーベルシュタイン(SF作家)
田原総一朗(ジャーナリスト)
音楽:小六禮次郎
特技監督:中野昭慶
監督:橋本幸治
助監督:大河原孝夫
ゴジラVSビオランテ
1989(平成元)年12月16日公開
配給:東宝
観客動員数:200万人
製作:田中友幸
ゴジラストーリー応募作品「ゴジラ対ビオランテ」 小林晋一郎・作より
音楽:すぎやまこういち
協力:防衛庁
特技監督:川北紘一
脚本・監督:大森一樹
≪ストーリー≫
ゴジラ(1984)
大黒島が噴火してから三ヶ月…第五八幡丸に乗っていた奥村宏は大黒島近辺で巨大な生物を目撃。巨大な生物の影響か、荒波により船は遭難する。翌日、ヨット航行をしていた新聞記者・牧吾郎は第五八幡丸を発見。中には多数のミイラ化した死体が。そして放射能の影響で巨大化したフナムシ(ショッキラ ス)に襲われる牧。間一髪のところを生存していた奥村宏に助けられる。生還した奥村は巨大生物のことを林田教授に相談する。林田教授はゴジラと確信。3ヶ 月前の大黒島の噴火によりゴジラが目覚めたのだ。パニックを防ぐため日本政府は報道封鎖。奥村も監禁される。林田教授に会った牧は研究所で奥村宏の妹、尚子に出会う。
太平洋沖にてソ連のミサイル原子力潜水艦が襲撃される。調査に向かったP3C対潜哨戒機が撮影した写真はゴジラそのものであった。緊迫するアメリカ・ソ連間を緩和するため政府はゴジラに関する報道を解禁する。厳戒態勢の中、ついにゴジラは伊浜原子力発電所の核燃料を狙い、静岡県に上陸。原子炉を襲い核燃料を吸収するゴジラ。が、突如渡り鳥とともに立ち去ってしまう。ゴジラのもつ磁性体に気づいた林田は、その帰巣本能を利用した作戦を政府に提案。合成した超音波によるゴジラを三原山へ誘導、三原山を故意に噴火させることで滅するというものだった。
一方、アメリカ、ソ連両国は戦術核によるゴジラ撃滅を要請。三田村首相は、これを拒む。両国が戦術核の使用を諦めたのも間もなく、東京湾にゴジラが出現。パニックに陥る東京。迎撃の準備をする自衛隊。そして三原山では火山噴火を誘発する準備が進められる。ついにゴジラが晴海埠頭に上陸。自衛隊の攻 撃もものともしないゴジラ。更に悪いことに、その戦闘の衝撃でソ連の衛星核ミサイルの起動スイッチが起動してしまう。
ゴジラVSビオランテ
1985 年、ゴジラ襲撃から一夜明けた新宿では、自衛隊が廃墟内の残留放射能を検査する一方、ゴジラの体の破片を回収する作業が行なわれていた。その最中、米国のバイオメジャーもG細胞の採取に成功、自衛隊に発見され銃撃戦となる。辛くも逃げ切った彼らだが、サラジア共和国のサラジア・シークレット・サービス工作 員のSSS9によって全員射殺され、G細胞も彼の手に渡る。サラジア共和国に運ばれたG細胞は、白神博士の研究室で小麦などの作物と融合させ、砂漠でも育つ植物を生む実験に使用されていた。しかし、G細胞争奪戦に敗れたバイオメジャーの策略で研究室は爆破され、白神博士はG細胞と共に最愛の娘・英理加を失う。
それから5年後、三原山内において再び活動を開始したゴジラに備え、国土庁はゴジラの体内の核物質を食べるバクテリアを利用した抗核エネル ギーバクテリア (ANEB) の必要性を強く認識したが、科学者の桐島は、それが核兵器を無力化する兵器にもなり、世界の軍事バランスを崩す引き金になるのではという危惧を抱いていた。しかし、日に日に活動を活発化させるゴジラに対抗し得るものとして、自衛隊の黒木特佐はその開発のために白神博士の協力を仰ぐ。一度は断った白神だ が、G細胞を1週間借り受けることを条件にANEB開発への協力を承諾する。
数日後、芦ノ湖に巨大なバラのような姿の怪獣が現れる。それは白神が娘の細胞を融合させたバラの命を救うために組み込んだG細胞の影響によって急激な成長を遂げた怪獣ビオランテであった。同じ頃、バイオメジャーによる、ANEBの引渡しを求める脅迫文が首相官邸に届く。応じぬ場合は三原山を爆破させゴジラを復活させるというその内容に、桐島 と自衛官の権藤は引渡しに応じるが、SSS9によりANEBは奪われ、さらに爆破された三原山からはゴジラが復活してしまう。
≪総論・見どころ≫
これらの作品は2つセットで見た方がいいだろうということで、同時に紹介する。ゴジラ1984は、ゴジラ生誕30周年を記念し、「メカゴジラの逆襲」から9年、眠りについていたゴジラの復活・完全に下火となっていた怪獣映画の隆盛を狙い、構想10年の東宝全社一大プロジェクトとして製作された。ゴジラVSビオランテはその続編であ り、一般公募作品の中からストーリーが選ばれた珍しい例でもある。これらの映画の魅力的な点については、「怖いゴジラへの原点回帰」「ゴジラ対人間の構図」「巨大生物が実際に現れた状況を想定した精確なシミュレーションによるプロット」といったポイントが挙げられる。昭和中期の作品より「子供のヒーロー」としてキャラク ター付されてきたゴジラのイメージをバッサリとリセットし、歩くだけでビルを薙ぎ倒し周囲を崩壊させ、放射熱線により近代建築を焼き払いながら有害な放射性物質をばらまく、人間にとってこの上ない脅威として映るべき大怪獣ゴジラが、第一作より長い時を経てゴジラ1984にて復活することになる。それに合わせ、ゴジラという怪獣の造形・演出もまたいわゆる「二代目ゴジラ」からは一新されたものとなった。足音は腹の底に響くような重低音、咆哮も初代ゴジラを参考に猛獣のようなうなり声が加わりおどろおどろしい。特に1984のゴジラ(84ゴジラ)の濃い造形は、人間の視点からは何を考えているのか分からない不気味な面構えも相俟って、ゴジラを人間とは相容れない化物として色濃く描写することに成功している。
さて、このような脅威的なゴジラに対し、人間側、特に政治や軍事に携わる人間がどう対応するか。この点を正確を期したシミュレーションに基づき描くことにより、2つの作品は災害パニックものとして大人の鑑賞に耐えるリアリティを提供できているのだともいえる。ゴジラ1984では、その当時の時事として米ソの外交関係が悪化した新冷戦の真っただ中であり、有名なペトロフ中佐事件 (1983)の記憶も新しい世相。このような世界情勢が映画の中で色濃く反映されており、当初ゴジラの存在を世間へ公開することを避けた日本政府が、ソ連原潜がゴジラによって撃沈されたことがトリガーとなり米ソ関係が一気に緊迫状態に陥ったのに慌てて対応を迫られるシーンや、米ソ政府が日本に対しゴジラへの戦術核の使用を容認するよう迫るシーンなどに社会派な演出が見て取れる。また、ゴジラVSビオランテでは、冷戦終結後、特撮映画製作への関与が解禁された自衛隊の全面協力を得て、実際の演習映像を交えながらゴジラに対する戦略・戦術的作戦行動がリアルに表現され、怪獣映画ファンのみならずSF・軍事などの面からも高い評価を受けた。エンドクレジットに「協力:防衛庁」って出た時のネームバリューはやはり錚々たるものがある。自衛隊その他さまざまな方面の専門家の協力を得ることで、トンデモ兵器だけではなく、実在する兵器を巧みに駆使して人間がゴジラという脅威にどう挑むか、その様子を的確にシミュレーション出来ている。また、VSビオランテでは当時の最先端科学技術であったバ イオテクノロジーを巡る政治的・倫理的問題も扱っており、そういった点からも、この2作を単純な怪獣映画ではなく、質の良い大人の鑑賞に堪える日本映画として紹介できると思う。
ゴジラをただの分けのわからない化物としてではなく、いち生物として特徴づけている(1984の帰巣本能やVSビオランテの抗核バクテリア云々の話)点も自分としては今までにない表現で面白いと感じた。
以下見どころ
ゴジラ1984
・小六禮次郎氏によるオーケストレーション
ゴジラといえば伊福部昭大先生だが、伊福部昭氏以外のゴジラ音楽として、個人的に一番好きなのが本作における小六禮次郎氏の音楽。「怖いゴジラ」のイメージぴったりの、おどろおどろしくも壮大でなおかつもの悲しげなBGMは一回は聴いておくべき。
・薙ぎ払い放射熱線
怖 いゴジラを最も印象的に魅せている場面。それまではウルトラ○ンのスぺシウム光線くらいの扱いだった放射熱線が、ここにきて一気にパワーアップ。湾岸地区に設置された兵器群を自衛隊員もろとも一発で焼き払った映像は、それまでの子供の味方なゴジラに慣れていた人から見れば軽くトラウマになったことだろう。
・三原山火口にゆっくり接近するゴジラ
山の上、崖の上などに視点を置き、下からせり上がるようにして歩いてくるゴジラを撮るシーンは多々あるのだが、個人的には1984のこのシーンが一番好き。本作におけるクライマックスの前振りとして、小六禮次郎氏の音楽とも合わせていい演出をしてる。
ゴジラVSビオランテ
・三原山火口より復活するゴジラ
ゴジラが火山の噴火と共に出現するシーンは「対メカゴジラ」の偽ゴジラ出現シーンを除けば、このVSビオランテとVSモスラのみ(VSモスラでは海底火山に飲み込まれたゴジラがマントルを泳いで(!?)噴火した富士山火口から再出現)。川北紘一監督による膨大な火薬を使った爆発演出は、1989年の映画と言えどCGでは決して真似できない迫力を出している。VSモスラはさらにそれの強化版といったところなので、こちらもこのシーンだけでもいいのでぜひ見てほしい。
・浦賀水道沖海戦
特撮映画における海上戦としてはこれがトップといっていいほどのクオリティ。東宝の誇る巨大特撮用プールにて撮影された、三原山より復活し芦ノ湖へと向かうゴジラと海上護衛艦隊+スーパーX2の海戦。はつゆき・はるな型護衛艦よりゴジラへ向け一斉射される対艦ミサイル群や立ち上る水柱、放射熱線を受け爆発炎上する護衛艦と迫力満点である。
・動く体長120m・体重20万トン
ビオランテはゴジラと戦った怪獣の中でも最重の怪獣である。そんなゴジラをも凌ぐ巨体をもつビオランテであるが、植獣形態では植物でありながら「移動することが可能」で、これを設定だけでなく実際に動かして撮影したシーンがある。着ぐるみにして全高3メートルにもおよびビオランテを、操演に32本のピアノ線を使用、スタッフも20人あまり が動員されて撮影された該当シーンの迫力たるや、劇中でゴジラもたじろぐレベル。。ちなみにこれが、特技監督の川北氏の当日の思いつきで動かされることになったわけで、一番驚いたのが現場のスタッフだったとか。
④「ガメラ2~レギオン襲来~」
我が名はレギオン。我々は大勢であるが故に
≪基本データ≫
1996(平成8)年7月13日 上映
配給:東宝
観客動員数:120万人
総指揮:徳間康快
脚本:伊藤和典
音楽:大谷幸
特別協力:防衛庁
特技監督:樋口真嗣
監督:金子修介
≪ストーリー≫
ギャ オスとの戦いから1年後の冬。北海道周辺に流星雨が降り注ぎ、その内の一つが支笏湖の北西約1キロ、恵庭岳近くに落下した。直ちに陸上自衛隊第11師団化 学防護小隊が出動し、さらに大宮駐屯地からも渡良瀬佑介二等陸佐や花谷一等陸尉たちが調査に派遣される。しかし、懸命の捜索にも関わらず隕石本体は発見で きなかった。一方、緑色のオーロラの調査に訪れ、偶然渡良瀬たちと出会った札幌市青少年科学館の学芸員・穂波碧は、隕石が自力で移動した可能性を示唆す る。それを裏付けるように、近郊ではビール工場のガラス瓶やNTTの光ファイバー網が消失するという怪現象が多発。そしてその発生地点は札幌市に向かい、 少しずつ移動していた。
隕石落下から5日目、ついに事件の元凶が姿を現す。札幌市営地下鉄南北線で電車がトンネル内で謎の生物に襲撃された。更にそれに呼応するかのように、高さ数十メートルの巨大な植物が地中に根を張りながらすすきののデパートを突き破り出現した。怪虫(レギオン)と植物(草体)は流星群と共に外宇宙から飛来したものであり、2つは共生関係にあるものと考えられた。群体は餌としてガラスや土などに含まれるシリコンを喰い、その分解過程で発生した大量の酸素で草体を育てる。穂波は、草体は種子を宇宙に打ち上げて繁殖するものと推測。コンピュータがシミュレー トした草体の爆発力は、札幌を壊滅させるに充分なものであった。草体の爆破準備が進む札幌に、三陸沖より浮上したガメラが飛来。ガメラはプラズマ火球で草体を粉砕した。しかしその直後、地下からおびただしい数の群体が現れ、見る見るうちにガメラを覆い尽くしていく。小さな群体の攻撃には成す術が無く、ガメ ラは退却する。その後、地下から羽を持つ巨大なレギオンが出現し、夜空に飛び去った。
解剖の結果や札幌での事件の分析などから、レギオンは電磁波によってコミュニケーションし、電磁波を発する物を自らを妨害する敵と見なして攻撃する習性を持っていると推測された。だがそれは、電磁波の過密する大都市が狙われることを示唆していた。そんな中、仙台市街地に新たな草体が出現する。札幌よりも温暖な仙台では草体の成長が速いため対応が間に合わず、種子発射は時間の問題となってしまう。全域に避難命令が発令された仙台市には、ガメラと交信した少女・草薙浅黄がスキー旅行に訪れていた。再び草体を駆逐すべく 飛来したガメラの前に巨大レギオンが出現。ガメラを上回る巨体と圧倒的な力で襲い掛かる巨大レギオンにガメラは苦戦を強いられる。草体の種子発射間際に巨大レギオンは地中へと姿を消し、ガメラは満身創痍の状態でもなお草体の元へ向かう。しかし時すでに遅くガメラは発射寸前で種子を受け止めるが爆発を食い止 められず、仙台は壊滅した。ガメラも全身が焼け爛れ、死んだように動かなくなってしまう。
ガメラによって2度の種子発射に失敗したレギオンは、総力で東京を目指すことが予測された。これ以前の自衛隊は災害派遣により出動していたが、日本政府は自衛隊に防衛出動を命じ、レギオンの予想進路上に防衛ラインを構築する。
≪総論・見どころ≫
リアルな怪獣映画といって真っ先に思い浮かべるのがこの映画「ガメラ2」。自分はガメラ2を「最良の怪獣映画」だと 思っている。怪獣映画の教科書といってもいいくらいである。上述したゴジラVSビオランテも、自衛隊の全面協力を得て、怪獣という災害に対し自衛隊がどのような災害出動(あるいは防衛出動)を取るかを精確なシミュレー ションに基づき描いた作品であるが、ガメラ2は更にその上を行くクオリティを誇る。ゴジラシリーズは怪獣対人間、あるいは怪獣対怪獣の闘いを迫力たっぷりに描くことには長けているのだが、実際に怪獣が現れた際、人間側がどう動くか、また一般人のケア(避難誘導やメディアを使った警戒発令など)をどうするかといった細かな描写には欠けているという一面もある。「平成ゴジラシリーズはロマン、平成ガメラシリーズはリアリティ」というコメントをどこかで見かけたことがあるが、全くその通りといえるほどに、平成ガメラシリーズ、特にこのガメラ2は「怪獣」という未曽有の災害に対するプロフェッショナルの対応、そしてそれに巻き込まれる一般人の様子を正確に演出することに長けている。本作の敵怪獣であるレギオンが冒頭すすきのに営巣した際のパニック描写、次に仙台にて営巣が確認された際の迅速な避難警報の発令、そして仙台壊滅後、レギオンの東京進出を阻止するための自衛隊出動要請の閣議決定発表など、本当に細かなところまで「実際に”こういうこと”が起こったら”どう”なるのか」が忠実にシミュレートされている。本編の主人公の一人として、陸上自衛隊大宮駐屯地の渡良瀬佑介二等陸佐を物語の中心に据えているというのもポイント。
また、敵怪獣であるレギオンの設定も非常に凝っている。レギオンの生態はハキリアリやハチ といった社会性昆虫をモチーフとされているが、攻撃性の高いレギオンが最初にビール工場、そして敵性音波に対抗すべくすすきのの地下に侵攻、より暖かな環境を求めて仙台・東京へと進撃していくさまは、レギオンという「生物」を生態学的な見地からこと細かく表現し、オーディエンスに怪獣という「生物」を現実的な視点から理解させ、より映画にリアリティを持たせることに腐心した結果であるといえるだろう。人間からの一切のコミュニケーションを拒否する未知なる生物、それらが群体をなし、なおかつ戦略的・戦術的に迫ってくるという設定は古今東西の怪獣映画では珍しく、どちらかといえばSFやファンタジーに多いだろう。レギオンはそういった意味で幅広いジャンルにおいても非常に良く設定が練りこまれたといえる存在であろう。何よりこのレギオン、超カッコいい!マザーレギオンのどこか幾何学的で無機質・金属的なデザインはこれまでの怪獣とは一線を画すデザインであり、その強さもまた、歴代の怪獣の中でもトップクラスの実力を誇っている。自分の一番好きな怪獣でもあるので、ぜひ一度見てほしいと思う。
また、ガメラ2に関わらず、平成ガメラシリーズでは自衛隊がとても強い。ゴジラシリーズでは完全なやられ役・かませ役として扱われる一般兵器群も、ガメラシリーズでは大活躍を見せる(決して怪獣側が弱いというわけでなく)。カッコいい自衛隊・兵器が観たいという人には、ゴジラシリーズよりもガメラシリーズの方をお勧めする。
以下みどころ
・オープニング
「隕石落下地点は、支笏湖の南西約1キロの地点!化防小隊に出動要請!」からの自衛隊真駒内駐屯地出動シーンは武者震いするほどカッコいい。
・足利最終防衛線構築
ス タッフインタビューによれば監督の金子修介氏は、幼少時反戦・反自衛隊主義の家庭で育ったそうだが、(勿論氏の現在の思想について悪意をもって何かを述べているわけではないが)そのような経歴の人が、こういう風に戦車の出動シーンを迫力たっぷりに描写できるのだなあと感銘を受けた。戦時における大空襲を経験したことを伺わせる消防隊のおっちゃんの名言など、このシーンではレギオンとの最終決戦に挑む人々の命がけの覚悟がよく描かれてもいる。
・マイクロ波ウェーブによる薙ぎ払い&着地とスライディングに並行した3連樋口撃ち
平成ガメラシリーズで特技監督を担った樋口監督は、爆発による炎の演出などに絶大な評価があり、平成ゴジラシリーズにおける川北監督の金粉まみれ火薬まみれのド派手演出や、昭和後期ゴジラシリーズにおける中野爆発(後述)とはまた違った魅力がある。それがよく分かるのが、レギオンが戦車隊の50%をマイ クロ波ウェーブで一気に薙ぎ払った時の爆発演出。また、俗に「樋口撃ち」と呼ばれるガメラのプラズマ火球3連発については、前作の「大怪獣空中決戦」からさらにパワーアップし演出が見られる。レギオンに奇襲したガメラがスライディング着地をかましながら流れるように3連発。男の夢である。
・「5体に1体はラインを突破。最終防衛ラインに向けて飛行中!」
強い(確信)な自衛隊のシーン。いやあの大編隊相手に高射砲で5体に4体落としてるのが凄いでしょ。ちなみに映像ではどう考えても弾幕が薄すぎるように見えるがあれは4~5発に1発間隔で混ぜてある曳光弾なので実際の弾数はもっと多いはず。このシーンはガメラ復活→レギオンとのリベンジ戦開幕につながる部分なので、自衛隊の徹底抗戦の構えも見られることでさらにテンションあがるシーンである。
References
【怪獣wiki特撮大百科事典 http://wiki.livedoor.jp/ebatan/】
【Wikipedia】
【 自衛隊イラク派遣5:若者照準、映画に協力 http://www.asahi.com/special/jieitai/kiro/040323.html】
【ゴジラ-特撮SIGHT http://www.k5.dion.ne.jp/~god-sf/index.html】
【みんなのシネマレビュー http://www.jtnews.jp/index.html】
【日本の軍事=安保環境と巨大怪獣映画 http://blog.goo.ne.jp/weltstadt_16c/e/7c08edf7a098cf3f2436c1d96f55b3c9】
【平成ガメラ Blu-Ray BOX 映像特典~15年目の証言~】
etc...
そのくらい自分の中に根付いている特撮映画であるが、最近またシリーズを見返すことがあり、子供のころは只々怪獣がカッコいいとか爆発スゲーとしか感じなかったのが、自分自身が大人になったからか「この 作品はこの技術とか描写がすごいなー」とか「このレベルの演出・ストーリーだったら大人の鑑賞に耐えるレベルの映画として他人にもお勧めできるなー」とか考えたりもできた。
で、これはいい機会ということで、「これだけ観とけば特撮怪獣映画のなんたるかが分かる!」といった感じのリストを作ってみようと思い立った次第である。特撮怪獣映画というあまり一般受けしないディープなジャンルの入門として見なくても、今回選んだのは単なる怪獣映画としてではなく大人の見る邦画としても十分通用するクオリティのものを選別したつもりなので、単純に「面白い映画が観たい」と いう需要にも応えられるものではないかな、と思う。
チープな文章になるかもしれないが、この記事を見て特撮怪獣映画に興味を持ったなら、ぜひ近所のビデオ屋でDVDをレンタルすることをお薦めする。
----------------------------------------------------------------------
さて、「特撮怪獣映画」と一概にいっても種類・本数が多く、ウルトラマンなどのヒーロー物も含めればとても完璧にカバーできるものではない。従って、今回まとめる範囲は「製作会社として主に東宝・大映から映画として配給された”怪獣が主役の”作品」に限ることにする。ウルトラマンシリーズなどテレビ・OVAを主体としたヒーロー物は含まれていない。こちらもこちらで面白いものは沢山あるんだけども。。。
また、映画の質を評価する基準として、私的なものではあるが【リアリティ】【特撮技術】【ロマン】の3つを考慮することにした(あくまで主観的なものなので、あしからず)。一つ目については、「巨大な怪獣が人間世界に現れる」という非日常な現象を、役者の演技だったり背景設定やストーリープロットであったりにより、どこまでフィクションを感じさせない現実感を伴ったものとして表現できているか、評価した。二つ目では、ミニチュアセットの組み方や怪獣の操演、破壊・爆発描写など、特撮映画が特撮映画たる技術を、どれだけ高いレベルで活用出来ているか、ということを重点的に評価した。最後の【ロマン】であるが、【ロマン】って何ぞやということを言い出すと人それぞれで概念が分かれるので、あくまで自分にとってのロマン性を基準にすることにした。項目の詳細については後ほど説明することとする。
このリストでは、上記の三つの評価項目に照らし合わせ、特にポイントの高いと思われる各作品について、見どころなどを紹介したいと思う。基本的に自分はシリアス志向の怪獣映画が好きで、人に勧めるならそういったものの方がいいとも考えているので、コミカル色の強い作品についてはそれが例え優れた作品であってもここには挙げないようにした(例えばキングコング対ゴジラなんかはこの例になる)。
---------------------------------------------------------------------
【リアリティ】
①「ゴジラ(1954)」
あのゴジラが、最後の一匹とは思えない。
≪基本データ≫
1954(昭和29)年11月3日上映 (併映:仇討珍剣法)
配給:東宝
観客動員数:961万人
製作:田中友幸
音楽:伊福部昭
特殊技術:圓谷英二(円谷英二)
監督:本多猪四郎
≪ストーリー≫
事件は一艘の貨物船の沈没事故から始まった…。救助に向かった船もまた炎上・沈没。大戸島に流れ着いた生存者は恐る恐る『巨大な怪物に襲われた】と語る。そして嵐の夜、その巨大な怪物は大戸島に現れ暴れまわった。
山根博士らは政府の命を受け災害調査団を結成し、大戸島へと向かう。博士の前にも姿を現した巨大怪物は、大戸島の伝説からゴジラと名づけられる。ゴジラは度重なる水爆実験により住処を追われて現れた怪物であった。一方、山根博士の娘・恵美子はかつての婚約者・芹沢を訪れる。そして彼の家で『オキシジェン・デストロイヤー』の実験を目の当たりにし、驚愕するのだった。決して口外してはならないと恵美子に告げる芹沢であった。
そしてゴジラは東京に上陸。放射能火炎により首都東京を火の海と化す。防衛隊の抵抗も効果のないままにゴジラは東京湾へと去っていった。ゴジラによる被災者に触れ悲劇の再来を避けたいと願った恵美子は尾形に『オキシジェン・デストロイヤー』のことを明かしてしまう。水中の酸素を一瞬のうちに無くし全ての生命を液化させる魔の存在…。しかし、あの巨大な怪物を葬るには、この悪魔の薬に手を染めるしかない。兵器化されるのを怖れる芹沢は頑なに『オキシジェン・デストロイヤー』の使用を拒否するのであったが、いつ訪れるとも知れないゴジラによる災害、被災者の姿を見た芹沢は一度だけの使用と決め、『オキシジェン・デストロイヤー』によって東京湾に潜むゴジラに一人で立ち向かっていく…。
≪総論・見どころ≫
「特撮怪獣映画」っていってこの「ゴジラ」を挙げないのは、マウントポジションでぶん殴られても文句は言えない所業。特撮怪獣映画という狭いジャンルだけでなく、日本映画全般においても抜群の知名度を誇るゴジラシリーズ、その第一作にして最高作である。ハリウッドでも公開され大ヒットとなった。本作があったからこそ、今日の特撮怪獣映画があるのだといっても過言ではないだろう。「特撮」という技術についても、今作によって、主に戦時中の戦意高揚映画の中で使われ戦後見捨てられかけていた特撮技術の価値が再認され、解体されかけていた「特殊技術課」が東宝内に再編成されたという経緯がある。そんな有名映画「ゴジラ」であるが、はそもそもが「子供向けの怪獣映画を作りたい」というモチベーションから製作が始まったわけではない。当時の時事として、ビキニ環礁での水爆実験と、第五福竜丸の被爆事件が社会問題となっていたことを受け、これに着想を得た田中氏によって「ビキニ環礁海底に眠る恐竜が、水爆実験の影響で目を覚まし、日本を襲う」という 企画が立てられた。そんな生い立ちを持つ本作が持つメッセージとは何かを考えてみると、勿論怪獣という架空の巨大生物の魅力というのもあるだろうが、それ以上に「核兵器への恐怖、決して癒えない戦争の傷跡」といったものに注視すべきであろう。作中ゴジラが東京を襲う際の侵攻ルートがB-29爆撃機の東京空襲ルートと全く同じという描写もあるし、ゴジラから逃げ遅れた母子の発した、迫りくる恐怖を前にしながら「もうすぐ(恐らく戦争で死んだ)父ちゃんのところに行けるからね」というセリフも印象的である。このように、ようやく戦争の傷跡から立ち直りかけた日本を、日本人の記憶に戦争の忌み子として最も色濃く刻みつけられている核兵器より生まれ出でた巨大怪獣が襲い首都東京を火の海にする、というストーリーは、強烈なインパクトとリアリティを伴い当時の観客に叩き付けられたのではないかと察せられる。それほどまでに、本作の内包する、単なる娯楽映画としてではなく骨太な社会派映画としての演出は現実味溢れるものなのである。ゴジラ登場時、人々が恐慌し逃げ回るシーンや、襲撃後死傷者で溢れかえる病院の悲惨なシーンなどでもエキストラがしっかりと演技しており、「未知なる=予知・迎撃手段のない巨大生物がいきなり都市部に現れたらどうなるか」という、後の特撮怪獣映画ではタブー とされがちだった命題が明確に的確に描かれている。
なお、当リストでは本作を【リアリティ】部門の中で紹介しているが、潤沢な予算と若き円谷組の意欲と試行錯誤によって実現されたハイクオリティなミニチュアセットや、音響・操演などの工夫など、特撮技術それ自体に関しても勿論後続の映画とは一線を画すレベルがあるので、こちらもぜひ注目してほしい。
以下見どころ
・大戸島にて~ゴジラ出現~
よくこの映画(というかゴジラ映画)の名場面として挙げられるシーン。元々はホラー映画を意識して作られたという本作では、作中初めから未知なる巨大生物の存在が示唆されるものの、肝心のゴジラは中々姿を現さない。劇中中盤に差し掛かろうかというタイミングで浮かび上がってくる伝説の怪獣「呉爾羅」。作中 の人物や映画を見ている観客が「ゴジラ」という怪獣を意識し、実像を各々にイメージしかけたころ、なんの前触れもなく大きな足音と共にいきなりそれが現れることになり、初めて怪獣映画を見る人はこれまでのギャップも相俟って大いに驚くことだろう。
・オキシジェン・デストロイアーの資料を燃やす芹沢博士
基本的に自分は怪獣映画において「人間を主体にしたドラマ」は必要ないと思っている。怪獣映画の主役は怪獣であり、映画に登場する人物はそれに巻き込まれる有象無象に過ぎず、群像劇ならばまだしも個人として怪獣を差し置いてスポットを当てられる存在であってはならないからだ(なのでそこらへんが過剰に演出されているミレニアムシリーズとかはあまり好みではない)。しかしながら、只々怪獣が暴れまわったりプロレスしているだけの映画もまた妙味に欠けるわけで、 その中に如何にさりげなく、しかして印象的に人間の心理(苦悩・葛藤)や奔走などを差し込むか、というのはリアリティを求める怪獣映画には必須な要素である。そして「ゴジラ」はその意味で最も成功している作品であるといっても過言ではなく、それが最も色濃く表れているのが芹沢博士関連の描写。戦争によって顔の半分を奪われ、さらにその戦争の禍根ともいえるゴジラによって自らの半生を費やした研究の成果を犠牲にせざるを得なかった彼の心情描写は、この物語には必要不可欠なスパイスであろう。彼の結末を考えれば、オキシジェン・デストロイアーの使用を覚悟し、後の世のために関連資料を全て荼毘に伏そうとと手に取り、数秒の間自身の人生の結晶であるそれらを見つめる博士が何を思ったのか、怪獣映画ファンではなく、いち研究者を目指すものとしても強く感情移入した場面である。
②「フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ(1966)」
「第1プラス線よし!第2マイナス線よし!」 「第4マイナス線よーし!」
≪基本データ≫
1966(昭和36)年7月31日上映
配給:東宝
製作:田中友幸、角田健一郎
音楽:伊福部昭
撮影:有川貞昌、富岡素敬
監督助手:中野昭慶
特技監督:円谷英二
監督:本多猪四郎
≪ストーリー≫
嵐の夜、三浦半島沖を航行する漁船・第三海神丸が大ダコに襲撃され沈没した。ただ一人、生き残った男が「仲間は全員、タコに続いて海から現れたフランケン シュタインみたいな怪物に喰われた」と繰り返し、さらに、噛み砕かれ吐き出されたかのような乗組員の衣服が引き上げられたことを受け、海上保安庁はフラン ケンシュタインの研究で有名な京都のスチュワート研究所へ連絡を取った。
スチュワート博士は「研究所で育てられ、1年前に富士で死んだはずのフラ ンケンシュタインが生き返り、漁船を襲ったのではないか」との問いに「仮に生き返ったとしても海にいたり人間を喰うことはあり得ない」とし、サンダと名付 けられたこのフランケンシュタインの世話をしていた所員の戸川アケミも「サンダはおとなしく素直だった」として、これらの疑いを全面否定する。
し かし、その後も三浦半島付近では海の怪物による被害が相次ぎ、スチュワート博士とアケミはフランケンシュタインの目撃報告をもとに富士山へ、間宮博士は横須賀へ、それぞれ向かった。果たして引き上げられた漁船からは海棲生物の細胞組織が、また山中では巨大な足跡が発見された。間宮の持ち帰った細胞組織がフ ランケンシュタインのものと判明した直後、曇天の羽田空港に巨大なフランケンシュタインが現れ、女性事務員を食らう。雲間から太陽が覗くや、そのフランケンシュタインは大慌てで海へと姿を消した。
一連の事件がフランケンシュタインによるものと判明し、対策会議に出席するため上京するスチュワート博士とアケミ。博士は山と海とにそれぞれフランケンシュタインがいるのではないかと想像する。会議では強い光や火に弱い海のフランケンシュタインの性質が間宮によって指摘され、市民に灯火要請が出される。その夜、遊覧船を襲ったフランケンシュタインは、ライトを浴びせられ境川から上陸。自衛隊によって太田橋付近の谷川へと誘導され、殺人光線による細胞組織の徹底消滅を図る「L作戦」が実行される。メーサーと放電攻撃によって感電死寸前となる怪物。ところがそこに、さらに巨大なもう一匹のフランケンシュタインが現れ、自衛隊を牽制して海の怪物を連れ去った。
≪総論・見どころ≫
設定などは異なるが、前年に公開された怪獣映画『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(こちらも後で紹介)の姉妹編、日米合作の特撮映画で、ホラー映画(あるいはSF映画)や小説として超有名な「フランケンシュタイン」を特撮映画に持ち込んだ意欲作。今年公開されたハリウッド版特撮映画「パシフィック・リム」の監督ギレルモ・デル・トロ氏もお気に入りの一品である本作が他の怪獣映画に比べ最も異質に映る点は、 「人間の姿をした巨大怪獣同士が争う」という点で、ごみごみした着ぐるみを着た怪獣同士のずんぐりむっくりした闘いには見られない柔軟性とスピードに富んだアクションには一見の価値がある。
本作において特にリアリティを感じる要素を挙げるとするならば、「自衛隊の本気」「怪獣による人間の捕食」の2点である。まず前者であるが、今作はフランケンシュタインVSフランケンシュタインVS自衛隊といいくらい、怪獣同士の争いの中で人間が被害者としてではなく同じリングに立つものとしてフィーチャーされている。上述の「ゴジラ」で言及 した等身大の人間ドラマは比較的少ないが、一方で本作において人間はただただ蹂躙される立場には収まらず、ひたすらプロレスを続ける怪獣同士の間に、自衛隊という人間の組織が割って入るという構図が取られる。この、自衛隊の面々が怪獣に対し徹底抗戦を取る姿が、本作においては非常に迫力たっぷりに描かれているのである。特にガイラに対するL作戦の準備シーンは見ごたえ抜群。太田橋付近の谷川において、野をかけ山をかけ、川にも飛び込みながら放電装置を設置する自衛隊員の様子はさながら実際に災害出動における作戦行動を行っているように見えた。(この自衛隊員は全て俳優を使っているそうで、実際幹部職には俳優名が当てられているのだが、ヒラの自衛隊員もそうなのかな?だとしたら本当に真に迫るすごい演技)
そしてもう一つが「人間を食べる怪獣」の描写。怪獣というのは第一には恐怖感を煽る存在でなければならないと自分は思っている。その恐怖感を煽るための要素というのが、都市部や町村の建築物の破壊だったり、人間を踏みつぶしたり焼き殺したりする様子だったりするのだが、最も強烈なのが「人を喰う」という設定であろう。実際自分より遥かに大きくて明らかに強暴そうな生物を見たら、人間はまず初めに「喰われるかもしれない」と恐怖するに違いない。本来被食者には成り得ない人間が「喰われる」という原始的恐怖を覚える存在。これもまた怪獣の魅力の一つである。怪獣映画が子供向きなものにシフトしていくにつれてこのような残虐表現はなくなっていったが、昭和初期には、本作をはじめとして「食人シーン」を含んだ怪獣映画は珍しくなかった。それらのうち、最も直截的に「人を喰う怪獣」を描いたのがこの作品におけるガイラである。何より恐ろしいことに、前述したとおりこの怪獣は人型なので、 演出の利点としていきなり走ったりなど、人間と同じような敏捷な動きが再現できるわけである。人を喰う怪獣が、ゆったりとしたスピードではなく猛ダッシュで迫ってくる・・・というのは言い様のなく恐ろしいこと。その点を効果的に演出し、怪獣の本来持つ根源的な恐怖を印象強く表現できていることが、本作品の最も特徴的な点でもあるだろう。
以下見どころ
・ガイラの羽田空港襲撃シーン
トラウマ。何が怖いって、女性を噛み千切るようにムシャムシャする食人シーンもそうだが、日光を感じ取ったガイラが一目散に海めがけて疾走して去っていくところ。自分を喰おうとしている怪獣が、こんなスピードで向かってきたら絶対逃げられないなと思う。
・自衛隊によるL作戦実行シーン
後々の特撮映画において人間側の主力兵器として活躍する「メーサー殺獣光線車」の初お披露目もこのシーン。「この威力!」。メーサーからのマイクロ波の当たった樹木がなぎ倒されていくさまも、特撮技術として妙味のある演出だ。
③「ゴジラ(1984)」and「ゴジラVSビオランテ(1989)」
ゴジラ(1984)
君たちは原子力発電所を襲うゴジラを見て何も感じなかったか?30年前その姿を現すまで、ゴジラは伝説の怪物だった。こうした伝説は世界中の神話に見られる。ゴジラは人類に対する滅びの警鐘だ。
ゴジラVSビオランテ
兄弟などではない。文字通りの分身だ。同じ細胞で一方は『動物』・・・ 一方は『植物』。
≪基本データ≫
ゴジラ1984
1984(昭和59)年12月15日 公開
配給:東宝
観客動員数:320万人
製作・原案:田中友幸
特別スタッフ:
竹内均(東京大学名誉教授)
青木日出雄(軍事評論家)
大崎順彦(工学博士)
クライン・ユーベルシュタイン(SF作家)
田原総一朗(ジャーナリスト)
音楽:小六禮次郎
特技監督:中野昭慶
監督:橋本幸治
助監督:大河原孝夫
ゴジラVSビオランテ
1989(平成元)年12月16日公開
配給:東宝
観客動員数:200万人
製作:田中友幸
ゴジラストーリー応募作品「ゴジラ対ビオランテ」 小林晋一郎・作より
音楽:すぎやまこういち
協力:防衛庁
特技監督:川北紘一
脚本・監督:大森一樹
≪ストーリー≫
ゴジラ(1984)
大黒島が噴火してから三ヶ月…第五八幡丸に乗っていた奥村宏は大黒島近辺で巨大な生物を目撃。巨大な生物の影響か、荒波により船は遭難する。翌日、ヨット航行をしていた新聞記者・牧吾郎は第五八幡丸を発見。中には多数のミイラ化した死体が。そして放射能の影響で巨大化したフナムシ(ショッキラ ス)に襲われる牧。間一髪のところを生存していた奥村宏に助けられる。生還した奥村は巨大生物のことを林田教授に相談する。林田教授はゴジラと確信。3ヶ 月前の大黒島の噴火によりゴジラが目覚めたのだ。パニックを防ぐため日本政府は報道封鎖。奥村も監禁される。林田教授に会った牧は研究所で奥村宏の妹、尚子に出会う。
太平洋沖にてソ連のミサイル原子力潜水艦が襲撃される。調査に向かったP3C対潜哨戒機が撮影した写真はゴジラそのものであった。緊迫するアメリカ・ソ連間を緩和するため政府はゴジラに関する報道を解禁する。厳戒態勢の中、ついにゴジラは伊浜原子力発電所の核燃料を狙い、静岡県に上陸。原子炉を襲い核燃料を吸収するゴジラ。が、突如渡り鳥とともに立ち去ってしまう。ゴジラのもつ磁性体に気づいた林田は、その帰巣本能を利用した作戦を政府に提案。合成した超音波によるゴジラを三原山へ誘導、三原山を故意に噴火させることで滅するというものだった。
一方、アメリカ、ソ連両国は戦術核によるゴジラ撃滅を要請。三田村首相は、これを拒む。両国が戦術核の使用を諦めたのも間もなく、東京湾にゴジラが出現。パニックに陥る東京。迎撃の準備をする自衛隊。そして三原山では火山噴火を誘発する準備が進められる。ついにゴジラが晴海埠頭に上陸。自衛隊の攻 撃もものともしないゴジラ。更に悪いことに、その戦闘の衝撃でソ連の衛星核ミサイルの起動スイッチが起動してしまう。
ゴジラVSビオランテ
1985 年、ゴジラ襲撃から一夜明けた新宿では、自衛隊が廃墟内の残留放射能を検査する一方、ゴジラの体の破片を回収する作業が行なわれていた。その最中、米国のバイオメジャーもG細胞の採取に成功、自衛隊に発見され銃撃戦となる。辛くも逃げ切った彼らだが、サラジア共和国のサラジア・シークレット・サービス工作 員のSSS9によって全員射殺され、G細胞も彼の手に渡る。サラジア共和国に運ばれたG細胞は、白神博士の研究室で小麦などの作物と融合させ、砂漠でも育つ植物を生む実験に使用されていた。しかし、G細胞争奪戦に敗れたバイオメジャーの策略で研究室は爆破され、白神博士はG細胞と共に最愛の娘・英理加を失う。
それから5年後、三原山内において再び活動を開始したゴジラに備え、国土庁はゴジラの体内の核物質を食べるバクテリアを利用した抗核エネル ギーバクテリア (ANEB) の必要性を強く認識したが、科学者の桐島は、それが核兵器を無力化する兵器にもなり、世界の軍事バランスを崩す引き金になるのではという危惧を抱いていた。しかし、日に日に活動を活発化させるゴジラに対抗し得るものとして、自衛隊の黒木特佐はその開発のために白神博士の協力を仰ぐ。一度は断った白神だ が、G細胞を1週間借り受けることを条件にANEB開発への協力を承諾する。
数日後、芦ノ湖に巨大なバラのような姿の怪獣が現れる。それは白神が娘の細胞を融合させたバラの命を救うために組み込んだG細胞の影響によって急激な成長を遂げた怪獣ビオランテであった。同じ頃、バイオメジャーによる、ANEBの引渡しを求める脅迫文が首相官邸に届く。応じぬ場合は三原山を爆破させゴジラを復活させるというその内容に、桐島 と自衛官の権藤は引渡しに応じるが、SSS9によりANEBは奪われ、さらに爆破された三原山からはゴジラが復活してしまう。
≪総論・見どころ≫
これらの作品は2つセットで見た方がいいだろうということで、同時に紹介する。ゴジラ1984は、ゴジラ生誕30周年を記念し、「メカゴジラの逆襲」から9年、眠りについていたゴジラの復活・完全に下火となっていた怪獣映画の隆盛を狙い、構想10年の東宝全社一大プロジェクトとして製作された。ゴジラVSビオランテはその続編であ り、一般公募作品の中からストーリーが選ばれた珍しい例でもある。これらの映画の魅力的な点については、「怖いゴジラへの原点回帰」「ゴジラ対人間の構図」「巨大生物が実際に現れた状況を想定した精確なシミュレーションによるプロット」といったポイントが挙げられる。昭和中期の作品より「子供のヒーロー」としてキャラク ター付されてきたゴジラのイメージをバッサリとリセットし、歩くだけでビルを薙ぎ倒し周囲を崩壊させ、放射熱線により近代建築を焼き払いながら有害な放射性物質をばらまく、人間にとってこの上ない脅威として映るべき大怪獣ゴジラが、第一作より長い時を経てゴジラ1984にて復活することになる。それに合わせ、ゴジラという怪獣の造形・演出もまたいわゆる「二代目ゴジラ」からは一新されたものとなった。足音は腹の底に響くような重低音、咆哮も初代ゴジラを参考に猛獣のようなうなり声が加わりおどろおどろしい。特に1984のゴジラ(84ゴジラ)の濃い造形は、人間の視点からは何を考えているのか分からない不気味な面構えも相俟って、ゴジラを人間とは相容れない化物として色濃く描写することに成功している。
さて、このような脅威的なゴジラに対し、人間側、特に政治や軍事に携わる人間がどう対応するか。この点を正確を期したシミュレーションに基づき描くことにより、2つの作品は災害パニックものとして大人の鑑賞に耐えるリアリティを提供できているのだともいえる。ゴジラ1984では、その当時の時事として米ソの外交関係が悪化した新冷戦の真っただ中であり、有名なペトロフ中佐事件 (1983)の記憶も新しい世相。このような世界情勢が映画の中で色濃く反映されており、当初ゴジラの存在を世間へ公開することを避けた日本政府が、ソ連原潜がゴジラによって撃沈されたことがトリガーとなり米ソ関係が一気に緊迫状態に陥ったのに慌てて対応を迫られるシーンや、米ソ政府が日本に対しゴジラへの戦術核の使用を容認するよう迫るシーンなどに社会派な演出が見て取れる。また、ゴジラVSビオランテでは、冷戦終結後、特撮映画製作への関与が解禁された自衛隊の全面協力を得て、実際の演習映像を交えながらゴジラに対する戦略・戦術的作戦行動がリアルに表現され、怪獣映画ファンのみならずSF・軍事などの面からも高い評価を受けた。エンドクレジットに「協力:防衛庁」って出た時のネームバリューはやはり錚々たるものがある。自衛隊その他さまざまな方面の専門家の協力を得ることで、トンデモ兵器だけではなく、実在する兵器を巧みに駆使して人間がゴジラという脅威にどう挑むか、その様子を的確にシミュレーション出来ている。また、VSビオランテでは当時の最先端科学技術であったバ イオテクノロジーを巡る政治的・倫理的問題も扱っており、そういった点からも、この2作を単純な怪獣映画ではなく、質の良い大人の鑑賞に堪える日本映画として紹介できると思う。
ゴジラをただの分けのわからない化物としてではなく、いち生物として特徴づけている(1984の帰巣本能やVSビオランテの抗核バクテリア云々の話)点も自分としては今までにない表現で面白いと感じた。
以下見どころ
ゴジラ1984
・小六禮次郎氏によるオーケストレーション
ゴジラといえば伊福部昭大先生だが、伊福部昭氏以外のゴジラ音楽として、個人的に一番好きなのが本作における小六禮次郎氏の音楽。「怖いゴジラ」のイメージぴったりの、おどろおどろしくも壮大でなおかつもの悲しげなBGMは一回は聴いておくべき。
・薙ぎ払い放射熱線
怖 いゴジラを最も印象的に魅せている場面。それまではウルトラ○ンのスぺシウム光線くらいの扱いだった放射熱線が、ここにきて一気にパワーアップ。湾岸地区に設置された兵器群を自衛隊員もろとも一発で焼き払った映像は、それまでの子供の味方なゴジラに慣れていた人から見れば軽くトラウマになったことだろう。
・三原山火口にゆっくり接近するゴジラ
山の上、崖の上などに視点を置き、下からせり上がるようにして歩いてくるゴジラを撮るシーンは多々あるのだが、個人的には1984のこのシーンが一番好き。本作におけるクライマックスの前振りとして、小六禮次郎氏の音楽とも合わせていい演出をしてる。
ゴジラVSビオランテ
・三原山火口より復活するゴジラ
ゴジラが火山の噴火と共に出現するシーンは「対メカゴジラ」の偽ゴジラ出現シーンを除けば、このVSビオランテとVSモスラのみ(VSモスラでは海底火山に飲み込まれたゴジラがマントルを泳いで(!?)噴火した富士山火口から再出現)。川北紘一監督による膨大な火薬を使った爆発演出は、1989年の映画と言えどCGでは決して真似できない迫力を出している。VSモスラはさらにそれの強化版といったところなので、こちらもこのシーンだけでもいいのでぜひ見てほしい。
・浦賀水道沖海戦
特撮映画における海上戦としてはこれがトップといっていいほどのクオリティ。東宝の誇る巨大特撮用プールにて撮影された、三原山より復活し芦ノ湖へと向かうゴジラと海上護衛艦隊+スーパーX2の海戦。はつゆき・はるな型護衛艦よりゴジラへ向け一斉射される対艦ミサイル群や立ち上る水柱、放射熱線を受け爆発炎上する護衛艦と迫力満点である。
・動く体長120m・体重20万トン
ビオランテはゴジラと戦った怪獣の中でも最重の怪獣である。そんなゴジラをも凌ぐ巨体をもつビオランテであるが、植獣形態では植物でありながら「移動することが可能」で、これを設定だけでなく実際に動かして撮影したシーンがある。着ぐるみにして全高3メートルにもおよびビオランテを、操演に32本のピアノ線を使用、スタッフも20人あまり が動員されて撮影された該当シーンの迫力たるや、劇中でゴジラもたじろぐレベル。。ちなみにこれが、特技監督の川北氏の当日の思いつきで動かされることになったわけで、一番驚いたのが現場のスタッフだったとか。
④「ガメラ2~レギオン襲来~」
我が名はレギオン。我々は大勢であるが故に
≪基本データ≫
1996(平成8)年7月13日 上映
配給:東宝
観客動員数:120万人
総指揮:徳間康快
脚本:伊藤和典
音楽:大谷幸
特別協力:防衛庁
特技監督:樋口真嗣
監督:金子修介
≪ストーリー≫
ギャ オスとの戦いから1年後の冬。北海道周辺に流星雨が降り注ぎ、その内の一つが支笏湖の北西約1キロ、恵庭岳近くに落下した。直ちに陸上自衛隊第11師団化 学防護小隊が出動し、さらに大宮駐屯地からも渡良瀬佑介二等陸佐や花谷一等陸尉たちが調査に派遣される。しかし、懸命の捜索にも関わらず隕石本体は発見で きなかった。一方、緑色のオーロラの調査に訪れ、偶然渡良瀬たちと出会った札幌市青少年科学館の学芸員・穂波碧は、隕石が自力で移動した可能性を示唆す る。それを裏付けるように、近郊ではビール工場のガラス瓶やNTTの光ファイバー網が消失するという怪現象が多発。そしてその発生地点は札幌市に向かい、 少しずつ移動していた。
隕石落下から5日目、ついに事件の元凶が姿を現す。札幌市営地下鉄南北線で電車がトンネル内で謎の生物に襲撃された。更にそれに呼応するかのように、高さ数十メートルの巨大な植物が地中に根を張りながらすすきののデパートを突き破り出現した。怪虫(レギオン)と植物(草体)は流星群と共に外宇宙から飛来したものであり、2つは共生関係にあるものと考えられた。群体は餌としてガラスや土などに含まれるシリコンを喰い、その分解過程で発生した大量の酸素で草体を育てる。穂波は、草体は種子を宇宙に打ち上げて繁殖するものと推測。コンピュータがシミュレー トした草体の爆発力は、札幌を壊滅させるに充分なものであった。草体の爆破準備が進む札幌に、三陸沖より浮上したガメラが飛来。ガメラはプラズマ火球で草体を粉砕した。しかしその直後、地下からおびただしい数の群体が現れ、見る見るうちにガメラを覆い尽くしていく。小さな群体の攻撃には成す術が無く、ガメ ラは退却する。その後、地下から羽を持つ巨大なレギオンが出現し、夜空に飛び去った。
解剖の結果や札幌での事件の分析などから、レギオンは電磁波によってコミュニケーションし、電磁波を発する物を自らを妨害する敵と見なして攻撃する習性を持っていると推測された。だがそれは、電磁波の過密する大都市が狙われることを示唆していた。そんな中、仙台市街地に新たな草体が出現する。札幌よりも温暖な仙台では草体の成長が速いため対応が間に合わず、種子発射は時間の問題となってしまう。全域に避難命令が発令された仙台市には、ガメラと交信した少女・草薙浅黄がスキー旅行に訪れていた。再び草体を駆逐すべく 飛来したガメラの前に巨大レギオンが出現。ガメラを上回る巨体と圧倒的な力で襲い掛かる巨大レギオンにガメラは苦戦を強いられる。草体の種子発射間際に巨大レギオンは地中へと姿を消し、ガメラは満身創痍の状態でもなお草体の元へ向かう。しかし時すでに遅くガメラは発射寸前で種子を受け止めるが爆発を食い止 められず、仙台は壊滅した。ガメラも全身が焼け爛れ、死んだように動かなくなってしまう。
ガメラによって2度の種子発射に失敗したレギオンは、総力で東京を目指すことが予測された。これ以前の自衛隊は災害派遣により出動していたが、日本政府は自衛隊に防衛出動を命じ、レギオンの予想進路上に防衛ラインを構築する。
≪総論・見どころ≫
リアルな怪獣映画といって真っ先に思い浮かべるのがこの映画「ガメラ2」。自分はガメラ2を「最良の怪獣映画」だと 思っている。怪獣映画の教科書といってもいいくらいである。上述したゴジラVSビオランテも、自衛隊の全面協力を得て、怪獣という災害に対し自衛隊がどのような災害出動(あるいは防衛出動)を取るかを精確なシミュレー ションに基づき描いた作品であるが、ガメラ2は更にその上を行くクオリティを誇る。ゴジラシリーズは怪獣対人間、あるいは怪獣対怪獣の闘いを迫力たっぷりに描くことには長けているのだが、実際に怪獣が現れた際、人間側がどう動くか、また一般人のケア(避難誘導やメディアを使った警戒発令など)をどうするかといった細かな描写には欠けているという一面もある。「平成ゴジラシリーズはロマン、平成ガメラシリーズはリアリティ」というコメントをどこかで見かけたことがあるが、全くその通りといえるほどに、平成ガメラシリーズ、特にこのガメラ2は「怪獣」という未曽有の災害に対するプロフェッショナルの対応、そしてそれに巻き込まれる一般人の様子を正確に演出することに長けている。本作の敵怪獣であるレギオンが冒頭すすきのに営巣した際のパニック描写、次に仙台にて営巣が確認された際の迅速な避難警報の発令、そして仙台壊滅後、レギオンの東京進出を阻止するための自衛隊出動要請の閣議決定発表など、本当に細かなところまで「実際に”こういうこと”が起こったら”どう”なるのか」が忠実にシミュレートされている。本編の主人公の一人として、陸上自衛隊大宮駐屯地の渡良瀬佑介二等陸佐を物語の中心に据えているというのもポイント。
また、敵怪獣であるレギオンの設定も非常に凝っている。レギオンの生態はハキリアリやハチ といった社会性昆虫をモチーフとされているが、攻撃性の高いレギオンが最初にビール工場、そして敵性音波に対抗すべくすすきのの地下に侵攻、より暖かな環境を求めて仙台・東京へと進撃していくさまは、レギオンという「生物」を生態学的な見地からこと細かく表現し、オーディエンスに怪獣という「生物」を現実的な視点から理解させ、より映画にリアリティを持たせることに腐心した結果であるといえるだろう。人間からの一切のコミュニケーションを拒否する未知なる生物、それらが群体をなし、なおかつ戦略的・戦術的に迫ってくるという設定は古今東西の怪獣映画では珍しく、どちらかといえばSFやファンタジーに多いだろう。レギオンはそういった意味で幅広いジャンルにおいても非常に良く設定が練りこまれたといえる存在であろう。何よりこのレギオン、超カッコいい!マザーレギオンのどこか幾何学的で無機質・金属的なデザインはこれまでの怪獣とは一線を画すデザインであり、その強さもまた、歴代の怪獣の中でもトップクラスの実力を誇っている。自分の一番好きな怪獣でもあるので、ぜひ一度見てほしいと思う。
また、ガメラ2に関わらず、平成ガメラシリーズでは自衛隊がとても強い。ゴジラシリーズでは完全なやられ役・かませ役として扱われる一般兵器群も、ガメラシリーズでは大活躍を見せる(決して怪獣側が弱いというわけでなく)。カッコいい自衛隊・兵器が観たいという人には、ゴジラシリーズよりもガメラシリーズの方をお勧めする。
以下みどころ
・オープニング
「隕石落下地点は、支笏湖の南西約1キロの地点!化防小隊に出動要請!」からの自衛隊真駒内駐屯地出動シーンは武者震いするほどカッコいい。
・足利最終防衛線構築
ス タッフインタビューによれば監督の金子修介氏は、幼少時反戦・反自衛隊主義の家庭で育ったそうだが、(勿論氏の現在の思想について悪意をもって何かを述べているわけではないが)そのような経歴の人が、こういう風に戦車の出動シーンを迫力たっぷりに描写できるのだなあと感銘を受けた。戦時における大空襲を経験したことを伺わせる消防隊のおっちゃんの名言など、このシーンではレギオンとの最終決戦に挑む人々の命がけの覚悟がよく描かれてもいる。
・マイクロ波ウェーブによる薙ぎ払い&着地とスライディングに並行した3連樋口撃ち
平成ガメラシリーズで特技監督を担った樋口監督は、爆発による炎の演出などに絶大な評価があり、平成ゴジラシリーズにおける川北監督の金粉まみれ火薬まみれのド派手演出や、昭和後期ゴジラシリーズにおける中野爆発(後述)とはまた違った魅力がある。それがよく分かるのが、レギオンが戦車隊の50%をマイ クロ波ウェーブで一気に薙ぎ払った時の爆発演出。また、俗に「樋口撃ち」と呼ばれるガメラのプラズマ火球3連発については、前作の「大怪獣空中決戦」からさらにパワーアップし演出が見られる。レギオンに奇襲したガメラがスライディング着地をかましながら流れるように3連発。男の夢である。
・「5体に1体はラインを突破。最終防衛ラインに向けて飛行中!」
強い(確信)な自衛隊のシーン。いやあの大編隊相手に高射砲で5体に4体落としてるのが凄いでしょ。ちなみに映像ではどう考えても弾幕が薄すぎるように見えるがあれは4~5発に1発間隔で混ぜてある曳光弾なので実際の弾数はもっと多いはず。このシーンはガメラ復活→レギオンとのリベンジ戦開幕につながる部分なので、自衛隊の徹底抗戦の構えも見られることでさらにテンションあがるシーンである。
References
【怪獣wiki特撮大百科事典 http://wiki.livedoor.jp/ebatan/】
【Wikipedia】
【 自衛隊イラク派遣5:若者照準、映画に協力 http://www.asahi.com/special/jieitai/kiro/040323.html】
【ゴジラ-特撮SIGHT http://www.k5.dion.ne.jp/~god-sf/index.html】
【みんなのシネマレビュー http://www.jtnews.jp/index.html】
【日本の軍事=安保環境と巨大怪獣映画 http://blog.goo.ne.jp/weltstadt_16c/e/7c08edf7a098cf3f2436c1d96f55b3c9】
【平成ガメラ Blu-Ray BOX 映像特典~15年目の証言~】
etc...

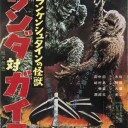
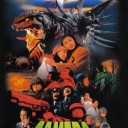
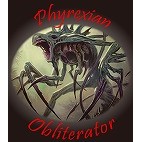
コメント